妻有新聞掲載記事一覧
- 新着順
- 人気順
-

「やり切る」、10年間の経験を糧に
美容室「SHEk」オープンの矢口佳奈子さん
「美容師免許の国家資格を取ってからが本番」と業界内でいわれ、シャンプーやカラーリングから始まり、すべて一人でできるまで2~4年かかるとされる美容師。
2024年12月14日号
-

十日町の時計が止まっている
来年4月末に市長選がある十日町市。来年6月末に許可権が満了するJR東・宮中取水ダムの水利権。市長選と同じく任期満了となる十日町市議会。動きがピタッと止まっている。時計の針を止めているのは誰か。いやいや、そもそも「十日町の時計」は動いていたのか…など、巷間話しは様々な憶測を呼んでいる。
JR東の水利権更新は、今回は10年前と事を大きく異にしている。不正取水による水利権取り消し後、新たに取得した水利権。来年の更新期はいわゆる「一般的な更新」、関係者はこれを「単純更新」と言う。いやいや単純なことなどこの案件にはない、というのが多くの市民感情だろう。来年の更新は、新規取得に比べ格段に事務手続きが簡素で、許可権者の国交省が地元新潟県知事に意見を求め、知事がOKを出せば、そのまま更新許可される。知事は地元の意見を聞くことができるが、聞く必要が無いと判断すれば、十日町市の意見は求めなくていい、そういう「単純更新」だ。
「発電の地元還元を」。来年4月の市長選に挑む新人が掲げる政策だ。JR東・宮中取水ダムで発電する信濃川発電所(小千谷市)。その関係する両自治体への「地元還元」を求め、両市関係者が連携して動いている。市民の間には「そうだよなぁ」と、ジワリと共感が広がりつつある。この論議もない十日町市議会の12月定例会だ。
任期満了の市長に対し、その進退を問うこともしない市議会だ。9日から12日までの一般質問では、誰もその進退を問わない、これはどうしたことか。ここでも「十日町の時計」は止まっている。いや止められているのか。
改選迫る市議会。動き始めているが、新人の名乗りがない。やはり時計が止まっている。大丈夫か、十日町市。
アナログ時計はネジを巻く。昨今のデジタル時計は止まっても分からない。2024年12月14日号
-

どう守る地域店、「会員一筋に」
来年4月「十日町市商工会」発足
5商工会が合併調印式
どう守る会員―。来年4月の合併に向け十日町市の川西、水沢、中里、松之山、松代町の5商工会長は4日、川西・千手中央コミュニティセンターで開かれた合併契約書調印式に臨み署名、捺印した。合併推進協議会長の瀬沼伸彦松代町商工会長は「3年半の協議は長く、これで止めようと思ったこともあった。いくつか問題もあると思うが、お互いにサポートしながら会員一筋にやっていきたい」と合併後の取り組み姿勢を話している。
県の財政再建に伴い4年前『商工会は1自治体1商工会に集約』、県補助金は『小規模事業者100未満は補助対象外』とする方針が示され、県商工会連合会の合併推進決議を受け協議を続けて来た。新たに発足する「十日町市商工会」は来年4月1日スタート。会員数は648事業所で、県内48商工会(来年4月合併後)のうち会員数は11番目。初年の令和7年度(2025)予算は約1億6200万円を予定する。
新事務所は旧十日町市社会福祉協議会川西支所を改修して設置。川西以外の商工会は5年後の令和12年度(2029)まで支所として2~3人の職員を置く予定だが、その後どうなるかは未定。「合併しても地域の小規模事業者を守ってほしい」という声にどう応えるか注目される。
2024年12月7日号
-

長期開催で来客分散、「経済効果地域に」
第9回大地の芸術祭 入込54万5931人
前回展4.9%減、1日来場者数「6091人」に増
「50日間の時はもう大変だったが、今回はお店もギュッとならず、いい間隔だったと思う。今回の形の方が、前回より、その前よりみんなが幸せだったのでは」。関口市長は第9回大地の芸術祭の入込数54万5931人(前回展比4・9%減)を2日の定例会見で発表。入込数は減少だが、ランチタイム時間の飲食店混雑や人気作品が密になり過ぎない状況だったことを指摘し「長期開催によるお客様の分散が、経済効果が地域に得られた」と見解を示している。
2024年12月7日号
-

「合志先生と出会い、生き方学ぶ」
田邊孝一さん(1982年生まれ)
恩師との出会いが、その後の生き方に大きく影響している。松之山小4年生の時、担任だった当時20歳代の合志淳教諭と出会った。「それまでは、学校って勉強して、いい点とって…っていう場所だと思っていたんですが…」、合志先生の言葉は違った。 『頭で覚える勉強も大事だが、楽しく、心で覚えることを学べ』。その場面はいまもはっきり憶えている。「その時からです、なんでも楽しく、辛いことでも、何事も前向きに考えるようになっていきました」。
いつも子どもたちと一緒に動き、一緒に考える恩師だった。「合志先生は、初雪が降ったら、外行くぞーって1限目から雪遊びに出て、そのまま授業時間が終わったりと。でも、いけないことをしたら凄く叱られましたが、いたずら程度では怒られたことはなかったです。人間味にあふれ、熱くて、皆が先生のことが大好きでした」。
生まれは東京・府中市。1987年、幼稚園年長の時、父の実家がある松之山に家族で移り住んだ。「あまり覚えていないんですが、保育園入ったばかりの時、『声かけたのに、こっち来るなって叩かれた』って、同級生に今でも言われます」と笑う。そこは子ども同士、すぐに地域にも仲間にも溶け込み、小中は陸上やアルペンスキーに取り組む。「練習はきつかったんですが、まぁ何とかなるか、でした。それに友だちや先輩たちが居たから続けられましたね」。さらに「教室でものまね大会を開いたりと、毎日が楽しかったです。調子に乗りすぎちゃうこともあるんですが、仲間たちがよく助けてくれてますね」。
松代高校へ進む。「進路に迷った時、友だちが持っていた進路パンフにビビビっときたんです」。4歳下の妹、8歳下の従弟の面倒を見ていたことから、「子どもが好きだなって思って」。長岡・北陸学園保育科に進学。「当時、保育士をめざす男子は少なく、女性80人に男性15人位でした。その分、男たちの団結力はすごかったですよ。いまでも仲良しです」。学園祭でのライブで影響を受け、「同級生でバンド作るかって。私はエレキギターを選び、毎日皆で練習、週5日は飲み会してました。楽しかったなぁー」。
保育士初任地は十日町市の私立保育園。学園時、出会いがあり結婚、4人の子たちのパパだ。「園でも家でも、子どもたちに遊んでもらってました。子どもの発想って本当に面白いですね」。ちょっと先を考え16年前、松之山・不老閣に転職。「保育士から介護の仕事、最初は戸惑いもありましたが、入所者さんから『いい男だ、いい男だー』なんて、おだてられて、毎日楽しく業務しています」。
学生時代からのバンド活動も続け、松之山出身の後輩と2人組デュオ『二つ星』を結成し、作詞作曲にも挑戦。十日町雪まつりや各所のイベントなどに出演した。バンドやデュオ解散後も歌への情熱は変らなかった。その時、『NHKのど自慢大会』出場のチャンスをつかんだ。「会場は中里アリーナでした。多くの皆さんの前で歌えたこと、最高の経験でした。結婚10周年だったので、妻への感謝を込め吉田山田の『日々』を歌いました」。
のど自慢出場で感じたのは、「出場された方々の歌のうまいこと。うまい人って、こういう人たちのことなんだって感じたんです」、感情の込め方、歌に強弱をつけるなど意識し練習している。のど自慢出場者との交流がいまも続く。「みんなで定期的に集まりカラオケで練習したり、良い刺激になっています。私にとって歌はなくてはならないものです」。
小学4年で出会った恩師、合志先生は今年3月、定年退職を迎えた。「同級生で、合志先生を囲む会を開き、皆で集まろうかって話しています。伝えたいことがいっぱいあるし、話したいことがいっぱいありますから」。
▼バトンタッチします
小宮山英樹さん
2024年12月7日号
-
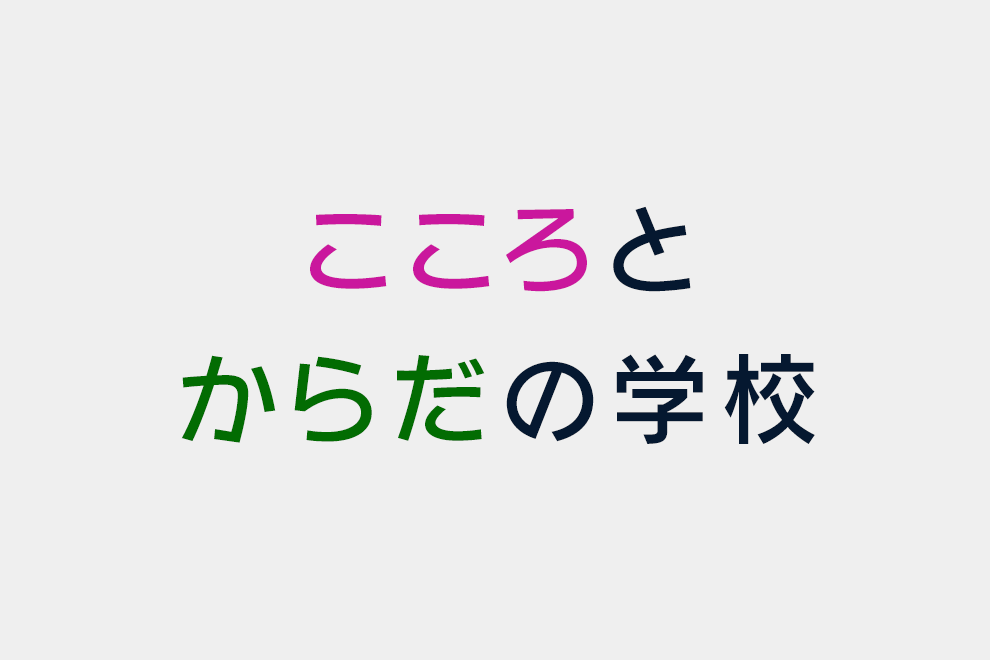
女性の頼もしい助っ人「モナリザタッチ」
デリケートゾーンケアに効果大
Vol 111
さて、こちらのコラムに書かせていただいてから、続々とデリケートゾーンの悩みを頂いています。今回は、「いかに楽しく毎日を過ごせるか」をめざし、性交障害、尿漏れ、萎縮性膣炎などを改善する女性のデリケートゾーンケアとして、いま大注目の膣レーザー治療「モナリザタッチ」についての続きです。
「膣にレーザー!?」と思う方も多いかと思いますが、科学的に効果は証明済み。年齢が進むと女性ホルモンの減少で若いころに比べて顔の皮膚のはりつやが失われるように、実は膣や外陰部も老化が生じ外陰部の違和感・灼熱感、かゆみ、におい、乾燥、黒ずみ、性交痛、おりものの増加、出血などさまざまな症状を生じます。尿漏れに関しては、骨盤底筋トレーニング器「エムセラ」と合わせて行うと良いといわれています。
女性ホルモンは第一に、肌のコラーゲンを増やす働きがあります。閉経すると膣の粘膜のコラーゲンが減り、粘膜が萎縮して荒れたり出血しやすくなったりすることで、おりものが増える、匂いが気になる、出血するなどが起こります。
外陰部はコラーゲンが減って皮膚が薄くなることで乾燥する、黒ずむ、かゆみが出る、ヒリヒリする、皮膚がたるむ、などが起きてきます。そこへ膣や外陰部にモナリザタッチでレーザーを照射すると、粘膜や皮膚のコラーゲンが再生されふっくらとします。まさに膣のアンチエイジングです。
女性ホルモンは第二に、膣の中にいる良い乳酸菌を増やす働きがあります。閉経して良い乳酸菌が減ると他の悪い菌が増えてしまい、匂いやおりものの増加の原因になります。コラーゲンを増やして良い土壌という膣粘膜を作り、膣内に良い乳酸菌という種を増やすということがデリケートゾーンケアの第一歩なのです。
今回は50~60歳という年齢の方を例に出しましたが、今までお話してきたようなデリケートゾーンの悩みは20代でも起こります。月経困難症で治療中の閉経前の若い女性も乾燥感や性交痛に悩みますし、産後の女性は尿漏れなどでも大いに悩みます。つまりデリケートゾーンケアは全年齢の女性にとって「いかに輝いて楽しく毎日を過ごせるか」のための大事なテーマです。
ちなみに、モナリザタッチによるレーザー治療は麻酔クリームを使うため、痛みに関してはさほど心配はいりません。私も体験しましたが、たまにチクチクするくらいでした。体験1回目の後の2ヵ月は、寒い時にトイレが近くなる、トイレに行きたいときに我慢できる力に不安を感じる、ふいに腹圧をかけたときに尿漏れが危ないと思う、ということを忘れていることができました。すると、仕事でも外出先でもプライベートで子どもと遊んでいても活動の範囲が広がりました。
現在、たかき医院では県内初のモナリザタッチ導入準備中です。(導入は12月下旬頃)。ご興味ある方はご連絡ください。ぜひ! たかき医院の「女性開運部」で一緒に輝きましょう!(たかき医院・仲栄美子院長)
2024年12月7日号
-

百人の市民、JR東日本交響楽団に拍手
「よろこびの歌」に感動
村山 朗 (会社員)
十日町の音楽文化は素晴らしい! 筆者は音楽好きではありますが、普段クラシック音楽は聞かないし、むしろクラシック嫌いです。そんな筆者でも知っている超有名曲、ベートーベンの交響曲第九番「合唱付き」のコンサートが、十日町市文化協会設立30周年記念ということで開かれました。
それも市民から百人の歌手を募って合唱するというではありませんか。初めて募集の話を聞いたときは、そんな人数が集まるのかと野次馬根性丸出しでしたが、杞憂に終わりました。女性に比べ男性が少ないものの百人以上の合唱団が見事に勢揃い。独唱の後の合唱が始まった瞬間、百人を超える合唱の音圧が二階席にいた筆者の体にドーンと届き、思わず鳥肌が立ちました。
半年以上の練習をやり通した合唱団員と素人集団をまとめ上げて本番に臨んだ指導者の苦労が喜びに代わり、聴衆と一体になった瞬間でした。
もう一つ、ステージにどうやって百人の合唱団とオーケストラを乗せるのか、これも興味津々でしたが、花道も使って打楽器を配し、ステージの前面に張り出しをつけ、見事に合唱団とオーケストラが一体化しておりました。
ところで、日本人なら多分だれでも歌える「よろこびの歌」~晴れたるあおぞら ただよう雲よ~の部分は全曲のうちのごく一部です。合唱だけが話題になりがちですが、全曲を通すと70分以上の大曲なんですね。はたして居眠りをせずに全曲聴き通せるのか、オーケストラ演奏の部分はどんな曲なのか。全曲通しては未聴だったため、予習のためCDを購入し、毎朝のように家族の迷惑も顧みずこの曲を流すようにしました。
まったく興味のない音楽でも聞く毎に親しみを覚え、聴き通すことも楽しみに変わるんですね。まさに名曲というべきでしょうか。こんなことを書くとクラシックファンには顰蹙を買うこと必至ですが、合唱部以外もとても素晴らしい。
さて、演奏したJR東日本交響楽団は、なんと発足30年を超えるアマチュアのオーケストラ。JR東日本の社員有志が仕事終了後に集まって定期的に練習を行っているそうです。オーケストラの演奏の良し悪しもよくわからない筆者ですが、プロの指揮者がまとめ上げた演奏は合唱に劣らず本当に聴きごたえがありました。
この素晴らしいコンサートを企画実行した主催者や裏方の皆さん、ホールのスタッフの仕事にも大きな拍手を送りたいと思います。5年後の35周年の演奏会も大いに期待しております。
2024年12月7日号
-

冬のヒーロー除雪隊
照井 麻美(津南星空写真部)
ロータリ除雪車やタイヤショベルを乗りこなし、私たちが朝出かけるまでの間に町中の道路を通れるようにしてくれている「豪雪地帯のヒーロー」除雪隊。
全国の除雪隊の始まりは北海道札幌市が始まりとされ、青森空港の除雪隊は『ホワイトインパルス』と呼ばれ、滑走路などの冬季でも滞りなく飛行機が離発着できるよう完璧なまでの除雪を行い全国的にも有名だ。
この地域の除雪は北の雪とは違い、重く湿っていて、扱いが難しいが、これだけキレイに除雪されている地域はほとんどない。
私が初めて目にした津南・十日町の冬道はスノータイヤじゃなくても走れるのではないかと思うほどきれいだった。
この地域に住んでいると当たり前の光景かもしれないが、民家の前やすぐ近くの道にあんな大きな重機が走り回って、大量の雪を退けていく。
私はそんな除雪隊がカッコイイなぁと早朝の作業を見るのがこれからの日課。
人口減少問題の中、除雪隊の人手不足も深刻な問題となっているが、昼夜問わず、生活に欠かせない必要不可欠な仕事に冬のヒーローとして、次の世代の除雪隊が増えることを切に願っている。
2024年12月7日号
-

学校再編、なぜ違うアプローチ
取り組み方法の違いは、その前段の「理念」の違いなのだろう。十日町市・津南町・栄村がいま共通して取り組む政課題の一つに「小中学校の再編」がある。そこに臨む行政姿勢に違いが見える。小学校17校、中学校10校を持つ十日町市は当初の学校再編への市民疑問を受け、再編計画をリセットし、新たな検討委員会による学校再編の方向性を地図に落とし込み、市民に提示している。二度目の再編案は10年先を見るが、行政・市教委主導というより、市民がリードし、協議している。
長野県最北の自治体、津南町と隣接の栄村は小学校1校、中学校1校を一体化する「文科省認定の義務教育学校」新設をめざす。その取り組みは村民参加のワークショップ方式。すでに22回を開き、その時々のテーマで村民主導で意見を交わし、ついに新設校の「校名」選定の段階まで来ている。一貫しているのは「村民が自ら作り上げる学校」。村教委は下支えに徹し、村民の主体性、自主性に重点を置く。全く新しい義務教育学校を作る、その大きな一歩の「校名」選びをいま全村対象に行っている。否が応でも関心が高まり、同時に教育内容も独自色を出す取り組みが平行して始まっている。県内外から問い合わせがある。
5年後までに小学校を町立1校にする方針を打ち出す津南町。その学校は「対等統合」という町教委の方針だが、「校名は今の津南小学校」、校歌も校章もそのままという。上郷小・芦ヶ崎小校区からは「対等統合ならなぜ新設小学校として校名や校歌を作らないのか」、疑問の声が出ている。津南町の学校再編は11年前に検討会が答申の内容をベースに学校再編を進めている。時代の変化、住民意識の変化があるなか、なぜ…と疑問が膨らむは町民たちだ。
同じ行政課題に、こうもアプローチが違うのはなぜか。12月議会が始まる。住民代表の議員の出番ですぞ。
2024年12月7日号
-

戻らないサケ、遡上わずか58匹
JR東日本・宮中取水ダム調査
10月高水温の影響か、河川環境の調査必須
北陸・甲信越地域から北海道まで11道県でサケの遡上・捕獲が前年比平均52%(国立研究開発法人水産研究・教育機構調べ、10月31日現在)と半減しているなか、中魚沼漁業協同組合(村山徹組合長)でもサケ遡上の最盛期である9月20日~11月10日までの期間に58匹(オス38匹、メス20匹)だけの遡上確認に留まり、「捕獲が少なすぎて採卵・人工授精ができなかった。昨年も49匹だけ。深刻な状況だ」(村山組合長)と危機感を強めている。同組合では「サケ回帰のデータは信濃川河川環境のバロメーター。地域から警鐘を鳴らしてほしい」と訴えている。
2024年11月30日号
-

「やり切る」、10年間の経験を糧に
美容室「SHEk」オープンの矢口佳奈子さん
「美容師免許の国家資格を取ってからが本番」と業界内でいわれ、シャンプーやカラーリングから始まり、すべて一人でできるまで2~4年かかるとされる美容師。
2024年12月14日号
-

十日町の時計が止まっている
来年4月末に市長選がある十日町市。来年6月末に許可権が満了するJR東・宮中取水ダムの水利権。市長選と同じく任期満了となる十日町市議会。動きがピタッと止まっている。時計の針を止めているのは誰か。いやいや、そもそも「十日町の時計」は動いていたのか…など、巷間話しは様々な憶測を呼んでいる。
JR東の水利権更新は、今回は10年前と事を大きく異にしている。不正取水による水利権取り消し後、新たに取得した水利権。来年の更新期はいわゆる「一般的な更新」、関係者はこれを「単純更新」と言う。いやいや単純なことなどこの案件にはない、というのが多くの市民感情だろう。来年の更新は、新規取得に比べ格段に事務手続きが簡素で、許可権者の国交省が地元新潟県知事に意見を求め、知事がOKを出せば、そのまま更新許可される。知事は地元の意見を聞くことができるが、聞く必要が無いと判断すれば、十日町市の意見は求めなくていい、そういう「単純更新」だ。
「発電の地元還元を」。来年4月の市長選に挑む新人が掲げる政策だ。JR東・宮中取水ダムで発電する信濃川発電所(小千谷市)。その関係する両自治体への「地元還元」を求め、両市関係者が連携して動いている。市民の間には「そうだよなぁ」と、ジワリと共感が広がりつつある。この論議もない十日町市議会の12月定例会だ。
任期満了の市長に対し、その進退を問うこともしない市議会だ。9日から12日までの一般質問では、誰もその進退を問わない、これはどうしたことか。ここでも「十日町の時計」は止まっている。いや止められているのか。
改選迫る市議会。動き始めているが、新人の名乗りがない。やはり時計が止まっている。大丈夫か、十日町市。
アナログ時計はネジを巻く。昨今のデジタル時計は止まっても分からない。2024年12月14日号
-

どう守る地域店、「会員一筋に」
来年4月「十日町市商工会」発足
5商工会が合併調印式
どう守る会員―。来年4月の合併に向け十日町市の川西、水沢、中里、松之山、松代町の5商工会長は4日、川西・千手中央コミュニティセンターで開かれた合併契約書調印式に臨み署名、捺印した。合併推進協議会長の瀬沼伸彦松代町商工会長は「3年半の協議は長く、これで止めようと思ったこともあった。いくつか問題もあると思うが、お互いにサポートしながら会員一筋にやっていきたい」と合併後の取り組み姿勢を話している。
県の財政再建に伴い4年前『商工会は1自治体1商工会に集約』、県補助金は『小規模事業者100未満は補助対象外』とする方針が示され、県商工会連合会の合併推進決議を受け協議を続けて来た。新たに発足する「十日町市商工会」は来年4月1日スタート。会員数は648事業所で、県内48商工会(来年4月合併後)のうち会員数は11番目。初年の令和7年度(2025)予算は約1億6200万円を予定する。
新事務所は旧十日町市社会福祉協議会川西支所を改修して設置。川西以外の商工会は5年後の令和12年度(2029)まで支所として2~3人の職員を置く予定だが、その後どうなるかは未定。「合併しても地域の小規模事業者を守ってほしい」という声にどう応えるか注目される。
2024年12月7日号
-

長期開催で来客分散、「経済効果地域に」
第9回大地の芸術祭 入込54万5931人
前回展4.9%減、1日来場者数「6091人」に増
「50日間の時はもう大変だったが、今回はお店もギュッとならず、いい間隔だったと思う。今回の形の方が、前回より、その前よりみんなが幸せだったのでは」。関口市長は第9回大地の芸術祭の入込数54万5931人(前回展比4・9%減)を2日の定例会見で発表。入込数は減少だが、ランチタイム時間の飲食店混雑や人気作品が密になり過ぎない状況だったことを指摘し「長期開催によるお客様の分散が、経済効果が地域に得られた」と見解を示している。
2024年12月7日号
-

「合志先生と出会い、生き方学ぶ」
田邊孝一さん(1982年生まれ)
恩師との出会いが、その後の生き方に大きく影響している。松之山小4年生の時、担任だった当時20歳代の合志淳教諭と出会った。「それまでは、学校って勉強して、いい点とって…っていう場所だと思っていたんですが…」、合志先生の言葉は違った。 『頭で覚える勉強も大事だが、楽しく、心で覚えることを学べ』。その場面はいまもはっきり憶えている。「その時からです、なんでも楽しく、辛いことでも、何事も前向きに考えるようになっていきました」。
いつも子どもたちと一緒に動き、一緒に考える恩師だった。「合志先生は、初雪が降ったら、外行くぞーって1限目から雪遊びに出て、そのまま授業時間が終わったりと。でも、いけないことをしたら凄く叱られましたが、いたずら程度では怒られたことはなかったです。人間味にあふれ、熱くて、皆が先生のことが大好きでした」。
生まれは東京・府中市。1987年、幼稚園年長の時、父の実家がある松之山に家族で移り住んだ。「あまり覚えていないんですが、保育園入ったばかりの時、『声かけたのに、こっち来るなって叩かれた』って、同級生に今でも言われます」と笑う。そこは子ども同士、すぐに地域にも仲間にも溶け込み、小中は陸上やアルペンスキーに取り組む。「練習はきつかったんですが、まぁ何とかなるか、でした。それに友だちや先輩たちが居たから続けられましたね」。さらに「教室でものまね大会を開いたりと、毎日が楽しかったです。調子に乗りすぎちゃうこともあるんですが、仲間たちがよく助けてくれてますね」。
松代高校へ進む。「進路に迷った時、友だちが持っていた進路パンフにビビビっときたんです」。4歳下の妹、8歳下の従弟の面倒を見ていたことから、「子どもが好きだなって思って」。長岡・北陸学園保育科に進学。「当時、保育士をめざす男子は少なく、女性80人に男性15人位でした。その分、男たちの団結力はすごかったですよ。いまでも仲良しです」。学園祭でのライブで影響を受け、「同級生でバンド作るかって。私はエレキギターを選び、毎日皆で練習、週5日は飲み会してました。楽しかったなぁー」。
保育士初任地は十日町市の私立保育園。学園時、出会いがあり結婚、4人の子たちのパパだ。「園でも家でも、子どもたちに遊んでもらってました。子どもの発想って本当に面白いですね」。ちょっと先を考え16年前、松之山・不老閣に転職。「保育士から介護の仕事、最初は戸惑いもありましたが、入所者さんから『いい男だ、いい男だー』なんて、おだてられて、毎日楽しく業務しています」。
学生時代からのバンド活動も続け、松之山出身の後輩と2人組デュオ『二つ星』を結成し、作詞作曲にも挑戦。十日町雪まつりや各所のイベントなどに出演した。バンドやデュオ解散後も歌への情熱は変らなかった。その時、『NHKのど自慢大会』出場のチャンスをつかんだ。「会場は中里アリーナでした。多くの皆さんの前で歌えたこと、最高の経験でした。結婚10周年だったので、妻への感謝を込め吉田山田の『日々』を歌いました」。
のど自慢出場で感じたのは、「出場された方々の歌のうまいこと。うまい人って、こういう人たちのことなんだって感じたんです」、感情の込め方、歌に強弱をつけるなど意識し練習している。のど自慢出場者との交流がいまも続く。「みんなで定期的に集まりカラオケで練習したり、良い刺激になっています。私にとって歌はなくてはならないものです」。
小学4年で出会った恩師、合志先生は今年3月、定年退職を迎えた。「同級生で、合志先生を囲む会を開き、皆で集まろうかって話しています。伝えたいことがいっぱいあるし、話したいことがいっぱいありますから」。
▼バトンタッチします
小宮山英樹さん
2024年12月7日号
-
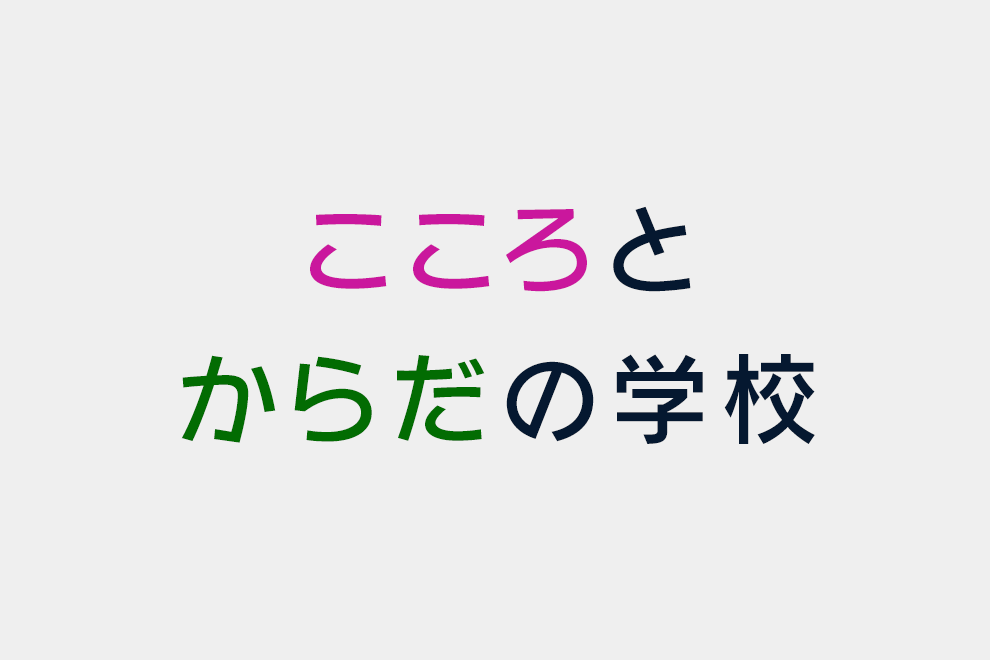
女性の頼もしい助っ人「モナリザタッチ」
デリケートゾーンケアに効果大
Vol 111
さて、こちらのコラムに書かせていただいてから、続々とデリケートゾーンの悩みを頂いています。今回は、「いかに楽しく毎日を過ごせるか」をめざし、性交障害、尿漏れ、萎縮性膣炎などを改善する女性のデリケートゾーンケアとして、いま大注目の膣レーザー治療「モナリザタッチ」についての続きです。
「膣にレーザー!?」と思う方も多いかと思いますが、科学的に効果は証明済み。年齢が進むと女性ホルモンの減少で若いころに比べて顔の皮膚のはりつやが失われるように、実は膣や外陰部も老化が生じ外陰部の違和感・灼熱感、かゆみ、におい、乾燥、黒ずみ、性交痛、おりものの増加、出血などさまざまな症状を生じます。尿漏れに関しては、骨盤底筋トレーニング器「エムセラ」と合わせて行うと良いといわれています。
女性ホルモンは第一に、肌のコラーゲンを増やす働きがあります。閉経すると膣の粘膜のコラーゲンが減り、粘膜が萎縮して荒れたり出血しやすくなったりすることで、おりものが増える、匂いが気になる、出血するなどが起こります。
外陰部はコラーゲンが減って皮膚が薄くなることで乾燥する、黒ずむ、かゆみが出る、ヒリヒリする、皮膚がたるむ、などが起きてきます。そこへ膣や外陰部にモナリザタッチでレーザーを照射すると、粘膜や皮膚のコラーゲンが再生されふっくらとします。まさに膣のアンチエイジングです。
女性ホルモンは第二に、膣の中にいる良い乳酸菌を増やす働きがあります。閉経して良い乳酸菌が減ると他の悪い菌が増えてしまい、匂いやおりものの増加の原因になります。コラーゲンを増やして良い土壌という膣粘膜を作り、膣内に良い乳酸菌という種を増やすということがデリケートゾーンケアの第一歩なのです。
今回は50~60歳という年齢の方を例に出しましたが、今までお話してきたようなデリケートゾーンの悩みは20代でも起こります。月経困難症で治療中の閉経前の若い女性も乾燥感や性交痛に悩みますし、産後の女性は尿漏れなどでも大いに悩みます。つまりデリケートゾーンケアは全年齢の女性にとって「いかに輝いて楽しく毎日を過ごせるか」のための大事なテーマです。
ちなみに、モナリザタッチによるレーザー治療は麻酔クリームを使うため、痛みに関してはさほど心配はいりません。私も体験しましたが、たまにチクチクするくらいでした。体験1回目の後の2ヵ月は、寒い時にトイレが近くなる、トイレに行きたいときに我慢できる力に不安を感じる、ふいに腹圧をかけたときに尿漏れが危ないと思う、ということを忘れていることができました。すると、仕事でも外出先でもプライベートで子どもと遊んでいても活動の範囲が広がりました。
現在、たかき医院では県内初のモナリザタッチ導入準備中です。(導入は12月下旬頃)。ご興味ある方はご連絡ください。ぜひ! たかき医院の「女性開運部」で一緒に輝きましょう!(たかき医院・仲栄美子院長)
2024年12月7日号
-

百人の市民、JR東日本交響楽団に拍手
「よろこびの歌」に感動
村山 朗 (会社員)
十日町の音楽文化は素晴らしい! 筆者は音楽好きではありますが、普段クラシック音楽は聞かないし、むしろクラシック嫌いです。そんな筆者でも知っている超有名曲、ベートーベンの交響曲第九番「合唱付き」のコンサートが、十日町市文化協会設立30周年記念ということで開かれました。
それも市民から百人の歌手を募って合唱するというではありませんか。初めて募集の話を聞いたときは、そんな人数が集まるのかと野次馬根性丸出しでしたが、杞憂に終わりました。女性に比べ男性が少ないものの百人以上の合唱団が見事に勢揃い。独唱の後の合唱が始まった瞬間、百人を超える合唱の音圧が二階席にいた筆者の体にドーンと届き、思わず鳥肌が立ちました。
半年以上の練習をやり通した合唱団員と素人集団をまとめ上げて本番に臨んだ指導者の苦労が喜びに代わり、聴衆と一体になった瞬間でした。
もう一つ、ステージにどうやって百人の合唱団とオーケストラを乗せるのか、これも興味津々でしたが、花道も使って打楽器を配し、ステージの前面に張り出しをつけ、見事に合唱団とオーケストラが一体化しておりました。
ところで、日本人なら多分だれでも歌える「よろこびの歌」~晴れたるあおぞら ただよう雲よ~の部分は全曲のうちのごく一部です。合唱だけが話題になりがちですが、全曲を通すと70分以上の大曲なんですね。はたして居眠りをせずに全曲聴き通せるのか、オーケストラ演奏の部分はどんな曲なのか。全曲通しては未聴だったため、予習のためCDを購入し、毎朝のように家族の迷惑も顧みずこの曲を流すようにしました。
まったく興味のない音楽でも聞く毎に親しみを覚え、聴き通すことも楽しみに変わるんですね。まさに名曲というべきでしょうか。こんなことを書くとクラシックファンには顰蹙を買うこと必至ですが、合唱部以外もとても素晴らしい。
さて、演奏したJR東日本交響楽団は、なんと発足30年を超えるアマチュアのオーケストラ。JR東日本の社員有志が仕事終了後に集まって定期的に練習を行っているそうです。オーケストラの演奏の良し悪しもよくわからない筆者ですが、プロの指揮者がまとめ上げた演奏は合唱に劣らず本当に聴きごたえがありました。
この素晴らしいコンサートを企画実行した主催者や裏方の皆さん、ホールのスタッフの仕事にも大きな拍手を送りたいと思います。5年後の35周年の演奏会も大いに期待しております。
2024年12月7日号
-

冬のヒーロー除雪隊
照井 麻美(津南星空写真部)
ロータリ除雪車やタイヤショベルを乗りこなし、私たちが朝出かけるまでの間に町中の道路を通れるようにしてくれている「豪雪地帯のヒーロー」除雪隊。
全国の除雪隊の始まりは北海道札幌市が始まりとされ、青森空港の除雪隊は『ホワイトインパルス』と呼ばれ、滑走路などの冬季でも滞りなく飛行機が離発着できるよう完璧なまでの除雪を行い全国的にも有名だ。
この地域の除雪は北の雪とは違い、重く湿っていて、扱いが難しいが、これだけキレイに除雪されている地域はほとんどない。
私が初めて目にした津南・十日町の冬道はスノータイヤじゃなくても走れるのではないかと思うほどきれいだった。
この地域に住んでいると当たり前の光景かもしれないが、民家の前やすぐ近くの道にあんな大きな重機が走り回って、大量の雪を退けていく。
私はそんな除雪隊がカッコイイなぁと早朝の作業を見るのがこれからの日課。
人口減少問題の中、除雪隊の人手不足も深刻な問題となっているが、昼夜問わず、生活に欠かせない必要不可欠な仕事に冬のヒーローとして、次の世代の除雪隊が増えることを切に願っている。
2024年12月7日号
-

学校再編、なぜ違うアプローチ
取り組み方法の違いは、その前段の「理念」の違いなのだろう。十日町市・津南町・栄村がいま共通して取り組む政課題の一つに「小中学校の再編」がある。そこに臨む行政姿勢に違いが見える。小学校17校、中学校10校を持つ十日町市は当初の学校再編への市民疑問を受け、再編計画をリセットし、新たな検討委員会による学校再編の方向性を地図に落とし込み、市民に提示している。二度目の再編案は10年先を見るが、行政・市教委主導というより、市民がリードし、協議している。
長野県最北の自治体、津南町と隣接の栄村は小学校1校、中学校1校を一体化する「文科省認定の義務教育学校」新設をめざす。その取り組みは村民参加のワークショップ方式。すでに22回を開き、その時々のテーマで村民主導で意見を交わし、ついに新設校の「校名」選定の段階まで来ている。一貫しているのは「村民が自ら作り上げる学校」。村教委は下支えに徹し、村民の主体性、自主性に重点を置く。全く新しい義務教育学校を作る、その大きな一歩の「校名」選びをいま全村対象に行っている。否が応でも関心が高まり、同時に教育内容も独自色を出す取り組みが平行して始まっている。県内外から問い合わせがある。
5年後までに小学校を町立1校にする方針を打ち出す津南町。その学校は「対等統合」という町教委の方針だが、「校名は今の津南小学校」、校歌も校章もそのままという。上郷小・芦ヶ崎小校区からは「対等統合ならなぜ新設小学校として校名や校歌を作らないのか」、疑問の声が出ている。津南町の学校再編は11年前に検討会が答申の内容をベースに学校再編を進めている。時代の変化、住民意識の変化があるなか、なぜ…と疑問が膨らむは町民たちだ。
同じ行政課題に、こうもアプローチが違うのはなぜか。12月議会が始まる。住民代表の議員の出番ですぞ。
2024年12月7日号
-

戻らないサケ、遡上わずか58匹
JR東日本・宮中取水ダム調査
10月高水温の影響か、河川環境の調査必須
北陸・甲信越地域から北海道まで11道県でサケの遡上・捕獲が前年比平均52%(国立研究開発法人水産研究・教育機構調べ、10月31日現在)と半減しているなか、中魚沼漁業協同組合(村山徹組合長)でもサケ遡上の最盛期である9月20日~11月10日までの期間に58匹(オス38匹、メス20匹)だけの遡上確認に留まり、「捕獲が少なすぎて採卵・人工授精ができなかった。昨年も49匹だけ。深刻な状況だ」(村山組合長)と危機感を強めている。同組合では「サケ回帰のデータは信濃川河川環境のバロメーター。地域から警鐘を鳴らしてほしい」と訴えている。
2024年11月30日号
