妻有新聞掲載記事一覧
- 新着順
- 人気順
-

地域医療支える拠点エリア
10年かけ完工、総事業費150億円で
県立十日町病院が核
10年余かけ総事業費150億円余で新築整備した地域中核病院・県立十日町病院(275床)が完工。同エリアには十日町市が建設の市医療福祉総合センター(建築費14億3300万円)があり、同センター内には県立十日町看護専門学校や地元医師会、訪問看護ステーションおむすびなど地域医療や介護・福祉に関わる8機関が入る。一帯は医療・福祉・教育の連携拠点として、住民の命を守り続ける責務を背負う。一方で、県立病院の事業決算は昨年度23億円の最終赤字を発表、今年度はさらに厳しい見通しが出ており、県立病院経営改革は必至の状況。地元の医療機関や市町村などと県立病院のさらなる連携が求められるなか、同エリアに集中の関係機関の役割が増す。
2024年6月15日号
-

ヒット商品「そばいなり」、おんなしょパワーで
平野八重子さん(1949年生まれ)
それは、『じろばた』開店後、5年ほど経った頃だった。「そばの消費拡大をしたいんだが…」、農協の担当者から言われた。開店準備の時のように仲間たちと談義を重ねた。「その時、大先輩の富井トヨさんが言ったんです。『祖母だったか曾祖母だったか、昔はいなりの中に蕎麦を入れていたと聞いたことがある』。
この富井さんのひと言
から始まっ
たんです」。ヒット商品『そばいなり』誕生の秘話である。
2024年6月15日号
-

気になる経済の行方
景気は「気」
清水 裕理 (経済地理学博士)
前回のオピニオンで、最近の経済の動きが気になると書きましたが、その続きです。
景気は、良い方向に上がると次に下がり、下がるとまた上がってと循環を繰り返します。その高低差が急であったり、長すぎたりすることがないように、考えます。
景気には「気」という言葉が入っているように、人々の気持ちが経済に影響を与えます。不安が広がると一気に景気が悪くなることがよくあります。そのため、経済金融政策はタイミングよく打つ必要があります。
さて、それでは今現在の日本の景気はどうかというと、数字的に、景気後退時期に入ったと言える状況になってきました。四半期毎の実質の国内総生産(GDP)が、前期比で連続3期プラスになっていないからです。3期といわず2期でも景気後退期に入ったと判断するのが、経済関係者の間で通説となっています。
その判断と公表は、米国では民間の専門機関が、日本では政府が行います。実際には、数字より、生活者として買物をしているときや、人の流れが分かるタクシーの運転手さんの方が、景気の変化を早く感じとることがあります。
そして、その対策として行う経済金融政策の手段に税や金利水準の調整などがあり、どの分野にそれらを適用するのが効果的であるかは、国の特徴により異なります。
例えば、米国は、経済における消費の割合が大きいのでその分野を中心に、中国は土地建物などの資産の分野、日本は、他国に比べて生産に占める割合が大きいのでその分野に適用するのが効果的と考えられると思います。
そして、日本における生産の分野を牽引しているのは、なんと言っても自動車産業です。
しかし、先週、気になるニュースが飛び込んできました。国土交通省は、国の定める自動車の型式認証制度について不正があったと発表し、それを受けて国内三大自動車メーカーのトップが揃って謝罪会見を行う事態が生じました。行政処分がなされるかもしれません。メーカーは「国の基準より厳しい条件で実施しており安全性に問題はない」という話もしています。
今回の問題の詳細がまだ分からず、どれだけ生産に影響を与えるのか分からないのですが…実際に、乗っていて国内メーカーの車の性能は優れていると感じることが多いです。それを実現してきたのは、積み重ねられてきた技術や技能があってであり、日々よい製品を届けようと切磋琢磨している現場があってこそ。その大切さは、忘れてはならないと思います。
2024年6月15日号
-

餌を狙うゴイサギ
南雲 敏夫(県自然観察指導員)
先日、田んぼの中の農道を移動中に普段あまり見かけない感じの鳥が田んぼに舞い降りた。
車でゆっくりと近づいてみたらゴイサギ。広い河川敷の田んぼにいても不思議ではないが近距離で見る事があまりない鳥なので、窓を静かに開けて撮影、ゴイサギが移動するのでこちらもゆっくりと車を移動。
このサギ類は遠くからでも人影を見るとあっという間に飛び去ってしまう、さすがに目が良い。車の陰から撮影しても姿を見せるとすぐに飛び立つ。しかし今回はうまく撮れた、田んぼの中のオタマジャクシでも狙っているのか、さかんに姿勢を低くしてついばんでいた。
ゴイサギの由来は、昔、醍醐天皇に貴族階級の一つの五位を与えられたところから五位鷺とある。詳しくは読者で調べて頂きたい。
このゴイサギの幼鳥を見た事があるが、全身に星空みたいな美しい模様があって星五位とも言われている。夜、大きな声で「クワッー」と鳴く鳥はこのゴイサギである。2024年6月15日号
-

母から娘、受け継ぐ「慈愛」
たかき医院 仲栄美子院長
「母の大きな愛は、生きる様々なことにつながっている」、いつも胸に抱いている想いだ。幼少の頃から母である、高木成子医師の医療と向き合う姿を見て育ち、母と同じ産婦人科医にあこがれを抱いていた。命が生まれるその瞬間に関わる母の姿には、子どもながらも「希望」を感じ、産婦人科への道を歩んだ。今春4月、院長の母を継ぎ、医療法人社団・たかき医院の2代目院長に就いた仲栄美子医師(48)。「肩書が変わっただけなんですけどね。今でも母と一緒に働いています。母は80歳になり、ちょうど良いバトンタッチの時期かなと。ただ母からはまだ学ぶことが多く、無理なく続けてほしいです」。
2024年6月15日号
-

どうする、ニュー・グリーンピア津南
どうする? この疑問符の行き先は津南町のニュー・グリーンピア津南(ニューGP津南)だ。業務委託の契約が来年2025年9月30日で満了する。この話題は昨年秋から巷間で交わされたが、公式の場にやっと登場した。12日開会の津南町議会6月定例議会、初日からの一般質問の場だ。江村大輔氏は2年前の桑原悠町長答弁を引き合いに、契約満了を向かえる1年3ヵ月前の現状を踏まえ、津南町観光の拠点であるニューGP津南の今後の在り方を迫った。注目は契約満了後の経営形態と、津南町所有を継続するのか、この論点だ。
所有形態の在り方、どんな選択肢があるかを問われ、桑原町長は「二つある」と示した。『町所有を続けるか』『法人が買うか』。さらに『その場合、資産評価、資産価値などによる評価額を見定める必要があり、さらに評価額での売却に必ずしもならない場合があり、現状では考えなければならない事が多く、軽々に答えられない』。2つの選択肢だけなのか、ここに町長・町行政の視点を感じる。一方、江村氏は「4つの選択肢がある」と持論。それは「現状の維持」「プロに経営を任せ収入を得る形」「指定管理」「売却」。10年の業務委託契約が満了する1年3ヵ月前なら、すでに机上では「その後」を検討しているはずだ。「軽々に言えない」ということは、具体的な協議が進んでいる証左でもあると言える。今月21日がニューGP津南を経営する株式会社津南高原開発の第20期株主総会だ。コロナ禍前の2019年度決算では売上11億円を超えていたが、以降、苦戦を強いられている。
契約期間満了は大きな節目だ。ここは所有する津南町の指導力が試される時だ。まさに「どうする」に応える時だ。379㌶余の広大な土地は、それだけで大きな魅力。「軽々に」売却はあり得ない選択だ。さて、どうする。2024年6月15日号
-

『ボクにはボクの夢がある、 キミにはキミの夢がある』
北村フミ子さん(1949年生まれ)
生徒に鏡を渡す。課題は自画像。「紙を丸くくり抜き、出た鼻から描きます」。渡された画用紙を前に生徒たちは鏡で自分の鼻を見ながら、鼻の頭から左右の小鼻、鼻筋、鼻の下、鼻の溝を描き、『次は口。上唇、下唇、筋があるね。よく見て、よーく見て』。
さらに顎を描き、目の周りを、左右の頬を描くと顔らしくなってきた。額、さらに首と続き、次に耳。『いよいよ目玉を入れるよ。さらに眉毛。次に髪の毛、左右の髪は違うよ、よく見てね…』。授業を再現するとこんな感じだった。その結果、個性たっぷりの自画像が出来上がった。
「生徒たちは、でき上がった自分の作品を見て、驚くと共に感動しますよ。この描き方は、私に絵の楽しさを教えてくれた松本キミ子先生です。昨年亡くなりましたが『人はリアリズムに描いたものには感動する』の言葉通りですね」。
2024年6月8日号
-
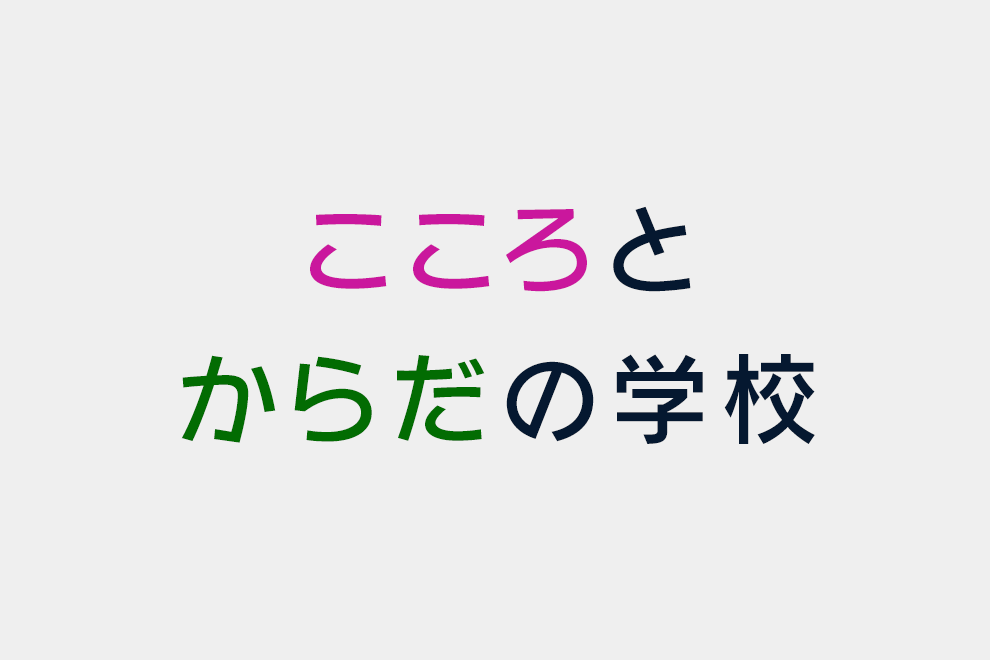
ぎっくり腰、その原因は「反り腰」
1回わずか3分、「おさんぽ整体」を
Vol 99
ここ2週間、ぎっくり腰でした。もともとぎっくり腰になりやすい話を以前させていただいたと思うのですが、年齢とともに押し寄せる胸椎(胸の背骨)と股関節の硬さのケアをきちんとしていないと、腰が胸椎と股関節の動きをカバーしようとして無理がかかり、「あ~…今やりました」ということになってしまうのです。そして、もう一つぎっくり腰の原因としてあるのは「反り腰」です。
女性で「反り腰」と言われたことのある方は結構いるのではないかと思います。つま先を軽く開いて、かかと・お尻・肩甲骨・後ろ頭を壁につけて立った時に、腰と壁の間に手のひらが2枚以上入る方は「反り腰」です。
もっと簡単にいえば、前屈をして床に手がつかない人、料理や洗い物をする際、キッチンのシンクにお腹をくっつけて立っていて、服がびしょびしょになっている方は「反り腰」の可能性が高いです。
実はこの反り腰、骨盤が正しい位置より前側に傾いてしまうため骨盤底筋が働きにくく、お腹の力が抜けてしまっているために、腰痛だけでなくポッコリお腹、口角が下がる、二重アゴ、ストレートネック、巻き肩・肩こり、ネガティブ思考などにもつながっていくといいます。また、女性特有の症状として反り腰は子宮下垂や子宮脱、月経不順、尿もれなどを引き起こします。
反り腰による不調に悩まされないために、まずは鏡を見ながら耳の穴、肩の中央(肩の骨の出っ張ったところ)、くるぶしが一直線になるように立ってみてください。自然と下腹に力が入りお尻の穴をギュッとすぼめているのではないでしょうか。この本来の私たちの正しい姿勢を維持しながら5分間深呼吸をするだけでかなりきついので、是非やってみてください。
そして、1回わずか3分で効果が出る、骨盤のゆがみを正し股関節をゆるめる「おさんぽ整体」をやってみましょう。できるだけ歩幅を大きくとって前へ足を踏み出すことがポイントです。
まず、両手を軽くお尻に当てお尻の筋肉が動いていることを感じながら1分間歩きます。次に上体を起こし、お腹の肉を前から軽く押さえて正しい姿勢を意識しながら1分歩きます。最後に足と腕をリズムよく振りながら脱力して、できるだけリラックスして1分歩きます。たったこれだけです。
ぎっくり腰になった直後はいつも、次はならないぞ! と張り切って色々するのですが、結局続かないからこそまた繰り返しているわけですが。
今年の春は少しお高い良いスニーカーを手に入れたので、晴れの日の爽やかな風の吹く中を小鳥のさえずりや、木々の優しい葉擦れの音などを堪能しながら、おさんぽ整体に出たいと思います。土市、新宮方面の方、時々ウロウロしています。よろしくお願いいたします。
足を怪我してしまっていたり、膝が痛くて歩けない、なかなか運動は習慣にならない、という方は是非70~80代の方が続々と杖無しで歩けるようになっているたかき医院の座るだけで骨盤底筋および体幹を鍛える器械に会いに来てくださいね!! (たかき医院・仲栄美子院長)2024年6月8日号
-

「不良老人にでもなるか!」
あの頃の学生気質は
長谷川 好文 (秋山郷山房もっきりや)
面白いもので年齢を重ねると、不意に若かった時のことを思い出すことが多くなるようだ。
先日、津南中等教育学校の脇を抜けて秋山へ向かっていた時のことだが、 ちょうど下校時間だったようで、三々五々、学生が校門を出て来るのにぶつかった。きちんと制服を着た真面目そうな学生だった。私服の学生は見当たらなかったが、おとなしそうで純粋なタイプのように感じた。そんな時に笑っちゃうが、60年も前の自分の通学姿が目に浮かんで来た。
通った学校は男子校だった。学生たちは制服を自分の好みに合わせて、学帽を油でテカテカに固めたり学生服の第一ボタンを外したりして、校門をくぐると少し与太った歩き方で国電の最寄りの駅までよく歩いた。近くに大学もあったせいか、駅までの道すがら古本屋とかラーメン屋、喫茶店も多く、路地裏には映画館やレコード店まであった。友達とワイワイ話しながら必ず寄り道をして帰った。
ぼくは中学からそのまま高校へ上がったのだが、その都市にある大学の継続校になったせいか、公立の有名校を落ちた学生の滑り止めになったようで、勉強のできる学生が入学して来た。それがなかなか面白い連中で、外から来た学生と馬が合ったのだろう、よく遊んだものである。
そんな友人達はとにかく変わった連中で、英語で教師に食ってかかる奴がいたり、ジャズやクラシックに詳しかったり、暇さえあれば美術館に通い、小説が好きで作家の癖をよく知っていた。演劇に狂っていたり、旅に目がなかったり、泳いだり、山を駆けたりと私の知らない世界を飛び回っているようだった。
その内に学校を抜け出し、落語や映画を見に塀を越えたものである。私は帰宅して勉強などしなかったから、いつまでも下から数えたほうが早い成績だったが、彼らは何時もそれなりの成績なのだ。
あの頃のぼく等はどちらかというと不良学生で、一見ちゃらんぽらんなことばかりして面白がっていた。ぼくにしてみればそんな不良っぽさが新鮮だったし、知らない世界を教えてもらった。不良であってもよいが、非行少年にはならないし、成績はいつもトップクラスなのだ。
何と云うのか生き方、暮らし方の強弱を彼等はわきまえていたのだろう。青春は好きなことに向かって狂っていればよかった時代だった。ただ授業中にちゃんと集中して、ちゃっかり復習までしていたのだろうことは想像できた。
今の津南の学生は近辺には映画館もない、レコード屋もありゃしない、喫茶店や書店すらないのだから せめてスマホのなかに潜り込んでSNSを駆使して超現実にワープしているのかも知らん。ぼくの時代にはそれぞれの好きなことに特化した不良学生が学校を、社会を面白くしてくれた。
今時の学生がきちんと制服を着て登下校する姿を見ると、学校の勉強だけで個性は作られるものではないのだがな~と昔を思い出した。
昨年だったか同窓会があって、元気でいる当時の担任の教師に聞いてみたことがある。現在あの学校はどうなっているのかと…。
「君らの時はいろんな学生がいて一番面白い時代だったが、今は学校が少し有名になったせいなのか、勉強が出来る学生ばかりになってしまった。親が子供に勉強しろ、勉強しろとばかり言うようになったのだろう」。
校則が金科玉条になってそれを破ると退学だ! 推薦は出来ない、と学校が現代の管理社会のモデルのようになってしまったとは思いたくはないが、まだ固まっていない若い学生たちというのは、いろんな個性が集まって不良でも出来が悪くても、良くても玉石混交で、それが交じり合って議論をして、喧嘩をして面白がって幅の厚い社会を支えられるものだと思う。だから教師にも個性豊かな学生を陰に回って支えて欲しいものだ!
昔の頃の元気はないが少し知恵を出して、今時の学生に不良老人からのエールでも送ってみたら面白いかなと思いつつ、布団をかぶった!2024年6月8日号
-

スイカズラ
中沢 英正(県自然観察保護員)
梅雨前のこの時期、唇形の小花をびっしりつけて存在をアピールしている。幹は蔓性で、日当たりのいい道端や斜面などで垂れ下がっていることが多い。
漢字にすると「吸蔓」で、花にある蜜を吸ったことからつけられた名である。子供にとっては宝の花だったのだ。
別名は「ニンドウ(忍冬)」、冬に緑の葉を保っていることから。津南周辺では雪が多く積もるためなのか葉は枯れ落ちてしまう。忍ぶことが難しいのである。雪国ではこの名称は似つかわしくない。
もう一つの別名に「キンギンカ(金銀花)」がある。花の咲き始めの白色を「銀」に、だんだんと黄味を帯びてくる様子を「金」に見たてたものである。花色の順だと「銀金花」だと思うのだが、語呂がいいからなのか、名づけ人が金に強い思い入れを持っていたためなのか…。
花には芳香があるが、夜になると更に強くなり、受粉を手伝ってくれる蛾を誘う。2024年6月8日号
-

地域医療支える拠点エリア
10年かけ完工、総事業費150億円で
県立十日町病院が核
10年余かけ総事業費150億円余で新築整備した地域中核病院・県立十日町病院(275床)が完工。同エリアには十日町市が建設の市医療福祉総合センター(建築費14億3300万円)があり、同センター内には県立十日町看護専門学校や地元医師会、訪問看護ステーションおむすびなど地域医療や介護・福祉に関わる8機関が入る。一帯は医療・福祉・教育の連携拠点として、住民の命を守り続ける責務を背負う。一方で、県立病院の事業決算は昨年度23億円の最終赤字を発表、今年度はさらに厳しい見通しが出ており、県立病院経営改革は必至の状況。地元の医療機関や市町村などと県立病院のさらなる連携が求められるなか、同エリアに集中の関係機関の役割が増す。
2024年6月15日号
-

ヒット商品「そばいなり」、おんなしょパワーで
平野八重子さん(1949年生まれ)
それは、『じろばた』開店後、5年ほど経った頃だった。「そばの消費拡大をしたいんだが…」、農協の担当者から言われた。開店準備の時のように仲間たちと談義を重ねた。「その時、大先輩の富井トヨさんが言ったんです。『祖母だったか曾祖母だったか、昔はいなりの中に蕎麦を入れていたと聞いたことがある』。
この富井さんのひと言
から始まっ
たんです」。ヒット商品『そばいなり』誕生の秘話である。
2024年6月15日号
-

気になる経済の行方
景気は「気」
清水 裕理 (経済地理学博士)
前回のオピニオンで、最近の経済の動きが気になると書きましたが、その続きです。
景気は、良い方向に上がると次に下がり、下がるとまた上がってと循環を繰り返します。その高低差が急であったり、長すぎたりすることがないように、考えます。
景気には「気」という言葉が入っているように、人々の気持ちが経済に影響を与えます。不安が広がると一気に景気が悪くなることがよくあります。そのため、経済金融政策はタイミングよく打つ必要があります。
さて、それでは今現在の日本の景気はどうかというと、数字的に、景気後退時期に入ったと言える状況になってきました。四半期毎の実質の国内総生産(GDP)が、前期比で連続3期プラスになっていないからです。3期といわず2期でも景気後退期に入ったと判断するのが、経済関係者の間で通説となっています。
その判断と公表は、米国では民間の専門機関が、日本では政府が行います。実際には、数字より、生活者として買物をしているときや、人の流れが分かるタクシーの運転手さんの方が、景気の変化を早く感じとることがあります。
そして、その対策として行う経済金融政策の手段に税や金利水準の調整などがあり、どの分野にそれらを適用するのが効果的であるかは、国の特徴により異なります。
例えば、米国は、経済における消費の割合が大きいのでその分野を中心に、中国は土地建物などの資産の分野、日本は、他国に比べて生産に占める割合が大きいのでその分野に適用するのが効果的と考えられると思います。
そして、日本における生産の分野を牽引しているのは、なんと言っても自動車産業です。
しかし、先週、気になるニュースが飛び込んできました。国土交通省は、国の定める自動車の型式認証制度について不正があったと発表し、それを受けて国内三大自動車メーカーのトップが揃って謝罪会見を行う事態が生じました。行政処分がなされるかもしれません。メーカーは「国の基準より厳しい条件で実施しており安全性に問題はない」という話もしています。
今回の問題の詳細がまだ分からず、どれだけ生産に影響を与えるのか分からないのですが…実際に、乗っていて国内メーカーの車の性能は優れていると感じることが多いです。それを実現してきたのは、積み重ねられてきた技術や技能があってであり、日々よい製品を届けようと切磋琢磨している現場があってこそ。その大切さは、忘れてはならないと思います。
2024年6月15日号
-

餌を狙うゴイサギ
南雲 敏夫(県自然観察指導員)
先日、田んぼの中の農道を移動中に普段あまり見かけない感じの鳥が田んぼに舞い降りた。
車でゆっくりと近づいてみたらゴイサギ。広い河川敷の田んぼにいても不思議ではないが近距離で見る事があまりない鳥なので、窓を静かに開けて撮影、ゴイサギが移動するのでこちらもゆっくりと車を移動。
このサギ類は遠くからでも人影を見るとあっという間に飛び去ってしまう、さすがに目が良い。車の陰から撮影しても姿を見せるとすぐに飛び立つ。しかし今回はうまく撮れた、田んぼの中のオタマジャクシでも狙っているのか、さかんに姿勢を低くしてついばんでいた。
ゴイサギの由来は、昔、醍醐天皇に貴族階級の一つの五位を与えられたところから五位鷺とある。詳しくは読者で調べて頂きたい。
このゴイサギの幼鳥を見た事があるが、全身に星空みたいな美しい模様があって星五位とも言われている。夜、大きな声で「クワッー」と鳴く鳥はこのゴイサギである。2024年6月15日号
-

母から娘、受け継ぐ「慈愛」
たかき医院 仲栄美子院長
「母の大きな愛は、生きる様々なことにつながっている」、いつも胸に抱いている想いだ。幼少の頃から母である、高木成子医師の医療と向き合う姿を見て育ち、母と同じ産婦人科医にあこがれを抱いていた。命が生まれるその瞬間に関わる母の姿には、子どもながらも「希望」を感じ、産婦人科への道を歩んだ。今春4月、院長の母を継ぎ、医療法人社団・たかき医院の2代目院長に就いた仲栄美子医師(48)。「肩書が変わっただけなんですけどね。今でも母と一緒に働いています。母は80歳になり、ちょうど良いバトンタッチの時期かなと。ただ母からはまだ学ぶことが多く、無理なく続けてほしいです」。
2024年6月15日号
-

どうする、ニュー・グリーンピア津南
どうする? この疑問符の行き先は津南町のニュー・グリーンピア津南(ニューGP津南)だ。業務委託の契約が来年2025年9月30日で満了する。この話題は昨年秋から巷間で交わされたが、公式の場にやっと登場した。12日開会の津南町議会6月定例議会、初日からの一般質問の場だ。江村大輔氏は2年前の桑原悠町長答弁を引き合いに、契約満了を向かえる1年3ヵ月前の現状を踏まえ、津南町観光の拠点であるニューGP津南の今後の在り方を迫った。注目は契約満了後の経営形態と、津南町所有を継続するのか、この論点だ。
所有形態の在り方、どんな選択肢があるかを問われ、桑原町長は「二つある」と示した。『町所有を続けるか』『法人が買うか』。さらに『その場合、資産評価、資産価値などによる評価額を見定める必要があり、さらに評価額での売却に必ずしもならない場合があり、現状では考えなければならない事が多く、軽々に答えられない』。2つの選択肢だけなのか、ここに町長・町行政の視点を感じる。一方、江村氏は「4つの選択肢がある」と持論。それは「現状の維持」「プロに経営を任せ収入を得る形」「指定管理」「売却」。10年の業務委託契約が満了する1年3ヵ月前なら、すでに机上では「その後」を検討しているはずだ。「軽々に言えない」ということは、具体的な協議が進んでいる証左でもあると言える。今月21日がニューGP津南を経営する株式会社津南高原開発の第20期株主総会だ。コロナ禍前の2019年度決算では売上11億円を超えていたが、以降、苦戦を強いられている。
契約期間満了は大きな節目だ。ここは所有する津南町の指導力が試される時だ。まさに「どうする」に応える時だ。379㌶余の広大な土地は、それだけで大きな魅力。「軽々に」売却はあり得ない選択だ。さて、どうする。2024年6月15日号
-

『ボクにはボクの夢がある、 キミにはキミの夢がある』
北村フミ子さん(1949年生まれ)
生徒に鏡を渡す。課題は自画像。「紙を丸くくり抜き、出た鼻から描きます」。渡された画用紙を前に生徒たちは鏡で自分の鼻を見ながら、鼻の頭から左右の小鼻、鼻筋、鼻の下、鼻の溝を描き、『次は口。上唇、下唇、筋があるね。よく見て、よーく見て』。
さらに顎を描き、目の周りを、左右の頬を描くと顔らしくなってきた。額、さらに首と続き、次に耳。『いよいよ目玉を入れるよ。さらに眉毛。次に髪の毛、左右の髪は違うよ、よく見てね…』。授業を再現するとこんな感じだった。その結果、個性たっぷりの自画像が出来上がった。
「生徒たちは、でき上がった自分の作品を見て、驚くと共に感動しますよ。この描き方は、私に絵の楽しさを教えてくれた松本キミ子先生です。昨年亡くなりましたが『人はリアリズムに描いたものには感動する』の言葉通りですね」。
2024年6月8日号
-
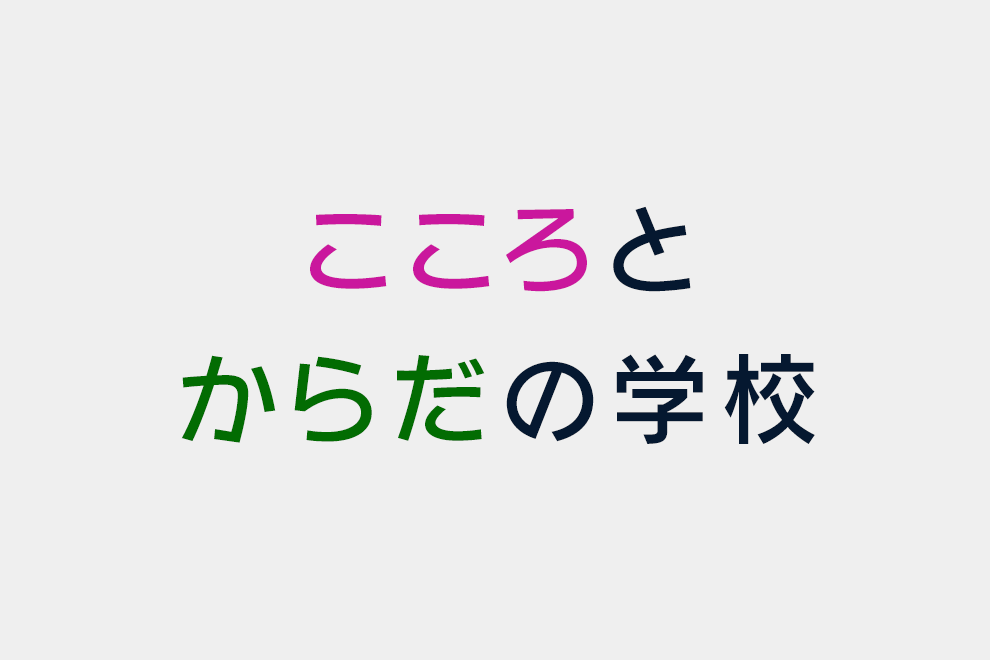
ぎっくり腰、その原因は「反り腰」
1回わずか3分、「おさんぽ整体」を
Vol 99
ここ2週間、ぎっくり腰でした。もともとぎっくり腰になりやすい話を以前させていただいたと思うのですが、年齢とともに押し寄せる胸椎(胸の背骨)と股関節の硬さのケアをきちんとしていないと、腰が胸椎と股関節の動きをカバーしようとして無理がかかり、「あ~…今やりました」ということになってしまうのです。そして、もう一つぎっくり腰の原因としてあるのは「反り腰」です。
女性で「反り腰」と言われたことのある方は結構いるのではないかと思います。つま先を軽く開いて、かかと・お尻・肩甲骨・後ろ頭を壁につけて立った時に、腰と壁の間に手のひらが2枚以上入る方は「反り腰」です。
もっと簡単にいえば、前屈をして床に手がつかない人、料理や洗い物をする際、キッチンのシンクにお腹をくっつけて立っていて、服がびしょびしょになっている方は「反り腰」の可能性が高いです。
実はこの反り腰、骨盤が正しい位置より前側に傾いてしまうため骨盤底筋が働きにくく、お腹の力が抜けてしまっているために、腰痛だけでなくポッコリお腹、口角が下がる、二重アゴ、ストレートネック、巻き肩・肩こり、ネガティブ思考などにもつながっていくといいます。また、女性特有の症状として反り腰は子宮下垂や子宮脱、月経不順、尿もれなどを引き起こします。
反り腰による不調に悩まされないために、まずは鏡を見ながら耳の穴、肩の中央(肩の骨の出っ張ったところ)、くるぶしが一直線になるように立ってみてください。自然と下腹に力が入りお尻の穴をギュッとすぼめているのではないでしょうか。この本来の私たちの正しい姿勢を維持しながら5分間深呼吸をするだけでかなりきついので、是非やってみてください。
そして、1回わずか3分で効果が出る、骨盤のゆがみを正し股関節をゆるめる「おさんぽ整体」をやってみましょう。できるだけ歩幅を大きくとって前へ足を踏み出すことがポイントです。
まず、両手を軽くお尻に当てお尻の筋肉が動いていることを感じながら1分間歩きます。次に上体を起こし、お腹の肉を前から軽く押さえて正しい姿勢を意識しながら1分歩きます。最後に足と腕をリズムよく振りながら脱力して、できるだけリラックスして1分歩きます。たったこれだけです。
ぎっくり腰になった直後はいつも、次はならないぞ! と張り切って色々するのですが、結局続かないからこそまた繰り返しているわけですが。
今年の春は少しお高い良いスニーカーを手に入れたので、晴れの日の爽やかな風の吹く中を小鳥のさえずりや、木々の優しい葉擦れの音などを堪能しながら、おさんぽ整体に出たいと思います。土市、新宮方面の方、時々ウロウロしています。よろしくお願いいたします。
足を怪我してしまっていたり、膝が痛くて歩けない、なかなか運動は習慣にならない、という方は是非70~80代の方が続々と杖無しで歩けるようになっているたかき医院の座るだけで骨盤底筋および体幹を鍛える器械に会いに来てくださいね!! (たかき医院・仲栄美子院長)2024年6月8日号
-

「不良老人にでもなるか!」
あの頃の学生気質は
長谷川 好文 (秋山郷山房もっきりや)
面白いもので年齢を重ねると、不意に若かった時のことを思い出すことが多くなるようだ。
先日、津南中等教育学校の脇を抜けて秋山へ向かっていた時のことだが、 ちょうど下校時間だったようで、三々五々、学生が校門を出て来るのにぶつかった。きちんと制服を着た真面目そうな学生だった。私服の学生は見当たらなかったが、おとなしそうで純粋なタイプのように感じた。そんな時に笑っちゃうが、60年も前の自分の通学姿が目に浮かんで来た。
通った学校は男子校だった。学生たちは制服を自分の好みに合わせて、学帽を油でテカテカに固めたり学生服の第一ボタンを外したりして、校門をくぐると少し与太った歩き方で国電の最寄りの駅までよく歩いた。近くに大学もあったせいか、駅までの道すがら古本屋とかラーメン屋、喫茶店も多く、路地裏には映画館やレコード店まであった。友達とワイワイ話しながら必ず寄り道をして帰った。
ぼくは中学からそのまま高校へ上がったのだが、その都市にある大学の継続校になったせいか、公立の有名校を落ちた学生の滑り止めになったようで、勉強のできる学生が入学して来た。それがなかなか面白い連中で、外から来た学生と馬が合ったのだろう、よく遊んだものである。
そんな友人達はとにかく変わった連中で、英語で教師に食ってかかる奴がいたり、ジャズやクラシックに詳しかったり、暇さえあれば美術館に通い、小説が好きで作家の癖をよく知っていた。演劇に狂っていたり、旅に目がなかったり、泳いだり、山を駆けたりと私の知らない世界を飛び回っているようだった。
その内に学校を抜け出し、落語や映画を見に塀を越えたものである。私は帰宅して勉強などしなかったから、いつまでも下から数えたほうが早い成績だったが、彼らは何時もそれなりの成績なのだ。
あの頃のぼく等はどちらかというと不良学生で、一見ちゃらんぽらんなことばかりして面白がっていた。ぼくにしてみればそんな不良っぽさが新鮮だったし、知らない世界を教えてもらった。不良であってもよいが、非行少年にはならないし、成績はいつもトップクラスなのだ。
何と云うのか生き方、暮らし方の強弱を彼等はわきまえていたのだろう。青春は好きなことに向かって狂っていればよかった時代だった。ただ授業中にちゃんと集中して、ちゃっかり復習までしていたのだろうことは想像できた。
今の津南の学生は近辺には映画館もない、レコード屋もありゃしない、喫茶店や書店すらないのだから せめてスマホのなかに潜り込んでSNSを駆使して超現実にワープしているのかも知らん。ぼくの時代にはそれぞれの好きなことに特化した不良学生が学校を、社会を面白くしてくれた。
今時の学生がきちんと制服を着て登下校する姿を見ると、学校の勉強だけで個性は作られるものではないのだがな~と昔を思い出した。
昨年だったか同窓会があって、元気でいる当時の担任の教師に聞いてみたことがある。現在あの学校はどうなっているのかと…。
「君らの時はいろんな学生がいて一番面白い時代だったが、今は学校が少し有名になったせいなのか、勉強が出来る学生ばかりになってしまった。親が子供に勉強しろ、勉強しろとばかり言うようになったのだろう」。
校則が金科玉条になってそれを破ると退学だ! 推薦は出来ない、と学校が現代の管理社会のモデルのようになってしまったとは思いたくはないが、まだ固まっていない若い学生たちというのは、いろんな個性が集まって不良でも出来が悪くても、良くても玉石混交で、それが交じり合って議論をして、喧嘩をして面白がって幅の厚い社会を支えられるものだと思う。だから教師にも個性豊かな学生を陰に回って支えて欲しいものだ!
昔の頃の元気はないが少し知恵を出して、今時の学生に不良老人からのエールでも送ってみたら面白いかなと思いつつ、布団をかぶった!2024年6月8日号
-

スイカズラ
中沢 英正(県自然観察保護員)
梅雨前のこの時期、唇形の小花をびっしりつけて存在をアピールしている。幹は蔓性で、日当たりのいい道端や斜面などで垂れ下がっていることが多い。
漢字にすると「吸蔓」で、花にある蜜を吸ったことからつけられた名である。子供にとっては宝の花だったのだ。
別名は「ニンドウ(忍冬)」、冬に緑の葉を保っていることから。津南周辺では雪が多く積もるためなのか葉は枯れ落ちてしまう。忍ぶことが難しいのである。雪国ではこの名称は似つかわしくない。
もう一つの別名に「キンギンカ(金銀花)」がある。花の咲き始めの白色を「銀」に、だんだんと黄味を帯びてくる様子を「金」に見たてたものである。花色の順だと「銀金花」だと思うのだが、語呂がいいからなのか、名づけ人が金に強い思い入れを持っていたためなのか…。
花には芳香があるが、夜になると更に強くなり、受粉を手伝ってくれる蛾を誘う。2024年6月8日号
