今週のトピックス一覧
- 新着順
- 人気順
-
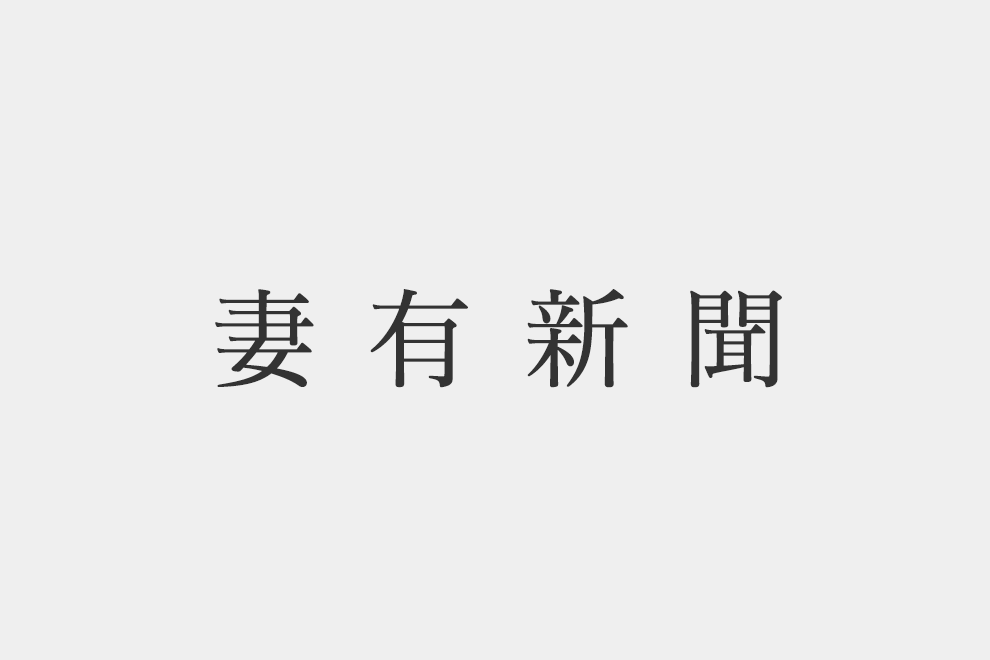
-

「病院守って」、地元署名2509筆
松代・松之山人口の約65%、全県1万筆超
県立松代病院 来春診療所化方針
来年4月から診療所化方針を県が示している、県立松代病院の存続を求める住民運動グループ「松代病院を守る会」(村山繁一代表)は先月28日、松代病院維持を求める2509筆署名を集め…
2025年9月13日号
-

-

「このプロジェクト進めて」の声も
桑原町長住民説明会、8会場で287人、今週末も
ニューGP民間売却
住民の関心は高かった。優先交渉権を不動産業やホテル業を行うイントランス(東京・渋谷区)に付与、現在ニュー・グリーンピア津南(NGP)売却に向け町が協議を続けるなか、桑原悠町長(39)による住民説明会が先月30日からスタート…
2025年9月6日号
-

「再交渉」強く求める
ニューGP売却で津南高原開発
自社応募明かし会見
ニュー・グリーンピア津南(NGP)売却で、町は優先交渉権を不動産業やホテル事業など手がけるイントランス(東京・渋谷区、資本金14億4442万円、何同璽代表)に付与しているが、町議6人が現従業員の雇用確保不透明などを理由に…
2025年8月30日号
-

「投機転売はない」、NGP津南売却で
イントランスと交渉中、10月以降 現津南高原開発と短期契約
注目を集める津南町のニュー・グリーンピア津南(NGP)売却。優先交渉権は不動産やホテル事業を手がける「イントランス」(東京・渋谷区、資本金14億4442万円、何同璽代表)に決定…
2025年8月23日号
-
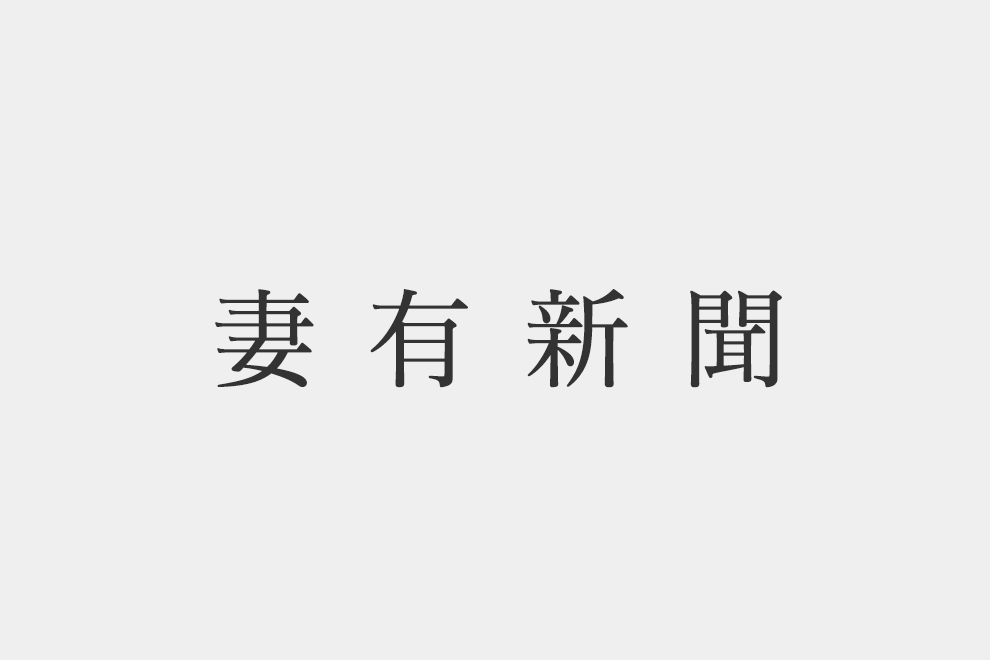
-

「空き家」活用で地域力アップ
国支援拡充、「民間主導」がカギ
全国空き家アド協 十日町支部が支援
高齢化、後継者不在で地域に残る「空き家」。危険度が増せば防災面では厄介者で、一方で移住者増や若者定住に向けては活用すれば大きな資源…
2025年8月16日号
-

妻有新聞速報
渇水二次被害、豪雨で田崩落
渇水でひび割れた田に、10日からの豪雨が浸透し田の一部が崩落する被害が津南町中子で発生している。今後の豪雨でさらに他の田でも被害が広がる恐れがあり、今後の降雨が心配される。
崩落した田は、魚沼コシヒカリの種を取る「採種田」。耕作者によると12日早朝、崩落に気づき町に連絡した。崩落は長さ約20㍍、深さ約2㍍ほどで、出穂したばかりの稲が、無残に崩れ落ちている。(8月12日午前11時50分発) -

-
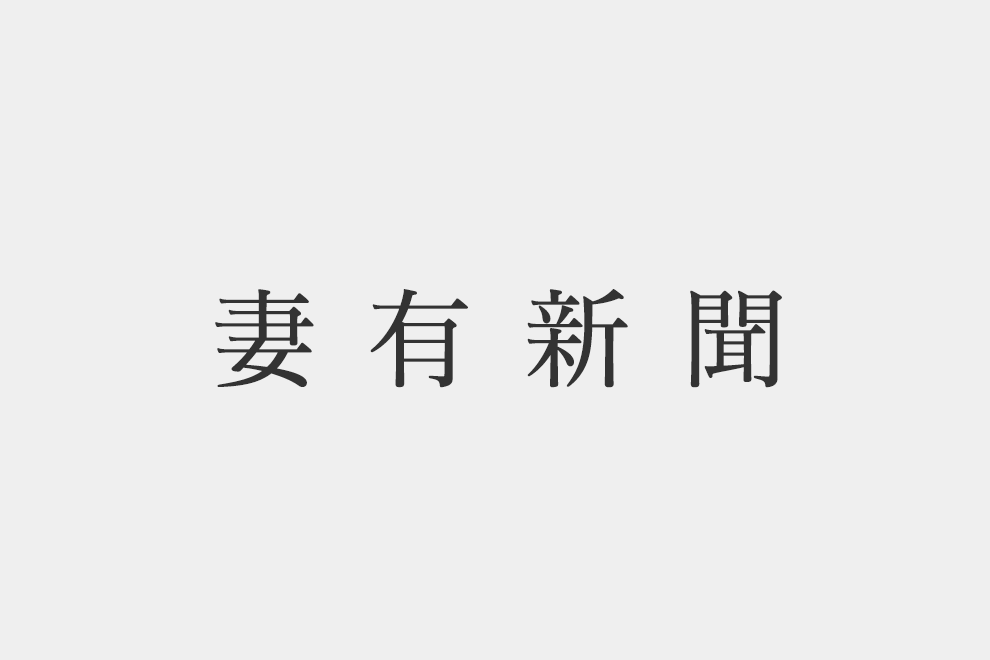
-

「病院守って」、地元署名2509筆
松代・松之山人口の約65%、全県1万筆超
県立松代病院 来春診療所化方針
来年4月から診療所化方針を県が示している、県立松代病院の存続を求める住民運動グループ「松代病院を守る会」(村山繁一代表)は先月28日、松代病院維持を求める2509筆署名を集め…
2025年9月13日号
-

-

「このプロジェクト進めて」の声も
桑原町長住民説明会、8会場で287人、今週末も
ニューGP民間売却
住民の関心は高かった。優先交渉権を不動産業やホテル業を行うイントランス(東京・渋谷区)に付与、現在ニュー・グリーンピア津南(NGP)売却に向け町が協議を続けるなか、桑原悠町長(39)による住民説明会が先月30日からスタート…
2025年9月6日号
-

「再交渉」強く求める
ニューGP売却で津南高原開発
自社応募明かし会見
ニュー・グリーンピア津南(NGP)売却で、町は優先交渉権を不動産業やホテル事業など手がけるイントランス(東京・渋谷区、資本金14億4442万円、何同璽代表)に付与しているが、町議6人が現従業員の雇用確保不透明などを理由に…
2025年8月30日号
-

「投機転売はない」、NGP津南売却で
イントランスと交渉中、10月以降 現津南高原開発と短期契約
注目を集める津南町のニュー・グリーンピア津南(NGP)売却。優先交渉権は不動産やホテル事業を手がける「イントランス」(東京・渋谷区、資本金14億4442万円、何同璽代表)に決定…
2025年8月23日号
-
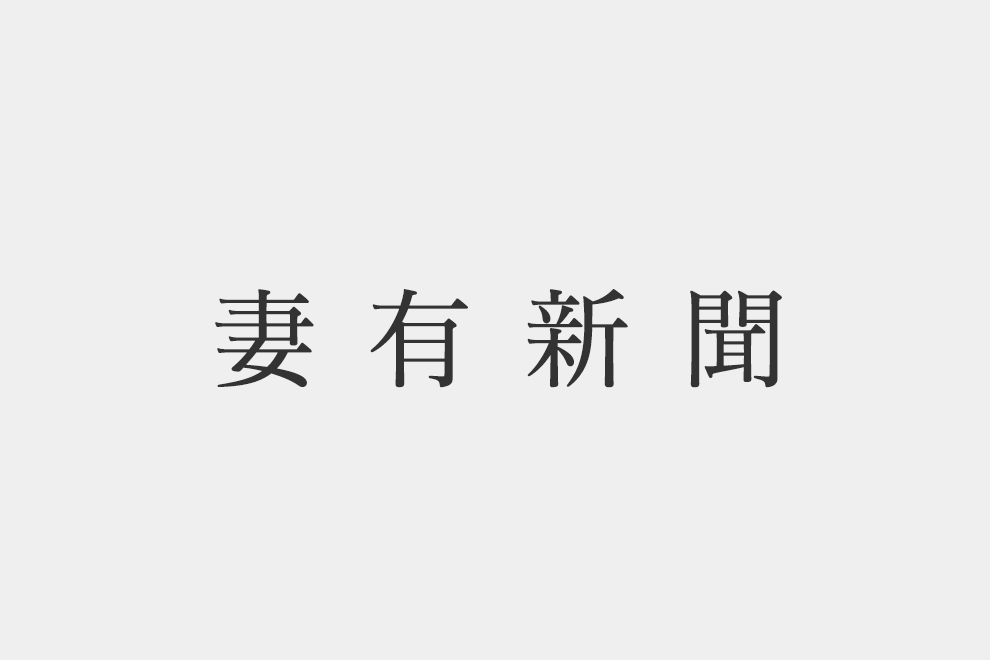
-

「空き家」活用で地域力アップ
国支援拡充、「民間主導」がカギ
全国空き家アド協 十日町支部が支援
高齢化、後継者不在で地域に残る「空き家」。危険度が増せば防災面では厄介者で、一方で移住者増や若者定住に向けては活用すれば大きな資源…
2025年8月16日号
-

妻有新聞速報
渇水二次被害、豪雨で田崩落
渇水でひび割れた田に、10日からの豪雨が浸透し田の一部が崩落する被害が津南町中子で発生している。今後の豪雨でさらに他の田でも被害が広がる恐れがあり、今後の降雨が心配される。
崩落した田は、魚沼コシヒカリの種を取る「採種田」。耕作者によると12日早朝、崩落に気づき町に連絡した。崩落は長さ約20㍍、深さ約2㍍ほどで、出穂したばかりの稲が、無残に崩れ落ちている。(8月12日午前11時50分発) -

